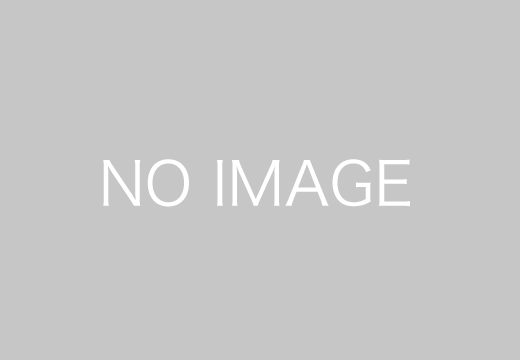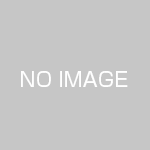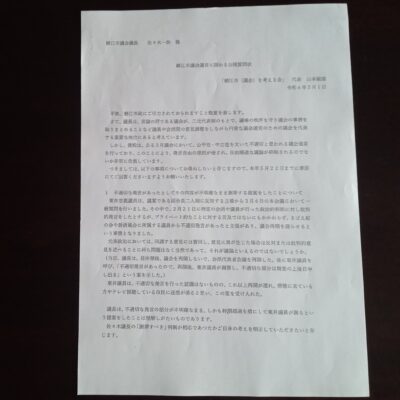日本のコメ政策について、テレビで特集がされた。
1 1960年代から食の欧米化が進み、コメ余りが生まれ、家畜の餌にまでなった。
2 1970年代になると、需要に見合った分だけ生産させることで、価格の下落を防ぐ減反政策が始まった。コメの価格は、米価審議会に諮って決められることで、国の管理下にあった。
3 1980年代には日米貿易摩擦が激しさを増し、農産物の自由化が求められたが、米だけは大正から外し続けた。自由化反対集会には、自民党の議員が激励に来るなど、自民党とのつながりが強くなった。農協を核とした集票マシンを重視してきた。
4 1993年東北地方を中心に大凶作が生まれ、コメ不足になった。政府はタイや中国からの緊急輸入に頼った。このことから、1995年に「政府備蓄米」制度が始まった。
5 1990年代になると、貿易自由化を求める米国の要求に抗しきれず、コメも部分的に自由化していった。
6 2018年には減反政策を撤廃した。中小のコメ農家を淘汰し、大規模な農家が自由に生産できる体制を整備し、コメの国際競争力を高めようとした。
7 コメの需要が減少と同じく、コメの生産量も減少していった。東京大学鈴木宣弘特任教授は、「自由化の流れの中で、米価は下がり続け、米価は半値以下になった、農家の所得は減り続け、もう「コメは作れない」と廃業する農家が続出していった。もう5年ほったらかしにしたら日本の稲作は崩壊してくる」と警鐘を鳴らされている。
8 行使した動きの中で、コメ農家が疲弊していった。機械類や肥料の経費により、コメ作りによる年間平均所得は97.000円(2024年12月農林水産省公表)となっている。
9 農業従事者は、2004年に約219万人であったものが、2024年には約111万人となり、平均寿命も69歳と高齢化が進んでいる。100万戸の農家がやめたのは、国がやめるように仕向けたのである。国家としての責任である。
10 コメ作りの問題は少子化対策にも似ている。
11 日本の食料の受給率は38%であり、これは安全保障にも関わる問題である。安全保障においては、普通の国は、食料はあるか、武器(軍事)はあるか、金はあるかを考える。しかし、。日本は食料にも金(財政)にも無頓着である。このことを今考えなければならない。